2007年7月 「窪島 誠一郎」さん

- 窪島 誠一郎(くぼしま せいいちろう)さん
「信濃デッサン館」「無言館」館主。作家。1941年東京生まれ。1979年長野県上田市に夭折画家の作品を展示する「信濃デッサン館」を、1997年には「無言館」を設立する。主な著作として『父への手紙』『「明大前」物語』『「信濃デッサン館」「無言館」遠景』『「無言館」の青春』『雁と雁の子-父・水上勉との日々』など多数。2005年、「無言館」の活動で第53回菊池寛賞を受賞。
『「無言館」に満ちる出征 画学生のひたむきな自己表現』
画学生のご遺族の家を北海道から種子島まで訪ね歩く
- 中川:
- 初めまして。私どもの会社は、見えないもの、つまり心や魂といったものを含めて“氣”といっているのですが、その“氣”の大切さをお伝えして皆がより幸せに暮らしていきましょうということを広めています。本誌の読者の方から、「無言館」のことを聞きまして、是非、館主の窪島さんにお話をうかがいたいと思った次第です。まず、「無言館」設立の経緯からお話しいただけますか。
- 窪島:
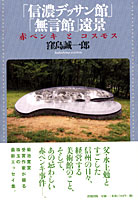 初めまして。私どもの会社は、見えないもの、つまり心や魂といったものを含めて“氣”といっているのですが、その“氣”の大切さをお伝えして皆がより幸せに暮らしていきましょうということを広めています。本誌の読者の方から、「無言館」のことを聞きまして、是非、館主の窪島さんにお話をうかがいたいと思った次第です。まず、「無言館」設立の経緯からお話しいただけますか。
初めまして。私どもの会社は、見えないもの、つまり心や魂といったものを含めて“氣”といっているのですが、その“氣”の大切さをお伝えして皆がより幸せに暮らしていきましょうということを広めています。本誌の読者の方から、「無言館」のことを聞きまして、是非、館主の窪島さんにお話をうかがいたいと思った次第です。まず、「無言館」設立の経緯からお話しいただけますか。- 中川:
- 亡くなった方が出征前に描いた貴重な作品とはいえ、ご両親が亡くなり更に代が替わっていけば、散逸してしまいますね。
- 窪島:
- 今まで自分が正視しないで、蔑ろにしてきた何かを突きつけられて、逃げ出したい感じがありました。僕は戦争が始まった年の生まれだけれど、全く戦争というものから目をそらせて生きてきました。絵描きになりたかったけれど高校中退して水商売をはじめて、高度成長期に金儲けにあくせくして、絵を買い集め34歳で若くして美術館の館主になって。敗戦のリバウンドですからね、あの高度成長期は。その甘い汁だけを吸って上昇志向で生きてきた男ですから。ご遺族と共有できる思いなんてそんなにないんです。いつも自分に自信が無くて、いつも空っぽの自分をそうではないように見せるのに一生懸命で。何かを偽って生きてきた感じ。でも、60を過ぎて所詮、空っぽは空っぽなのだと気づいた。そういう男が、ご遺族の方から「感謝しています」なんて言われる。そして、奇特なことをしている、いいことをしているようにメディアに取り上げられる… そういうのって、いたたまれない気持ちになるんです。もっと適当な人が居るのではという気持ちになりました。
- 中川:
- そうですか。でも、実際にこうして窪島さんが美術館を建ててくださって多くの人がその方々の絵を見ることができるのですから。皆さんの絵は、家族を描いたものが多いですね。身近な一番大事な存在を出征前の短い時間に思いを籠(こ)めて描かれたのでしょう。
- 窪島:
- そう、学生結婚していた妻や、恋人、妹、父母… 自分を愛して支えてくれた、そういう人々への深い感謝、思いやりを描いた。そこには、濃密な凝縮された時間がある。私たちが戦後何十年かで失ってしまった濃密な時間です。何もかも忘れてひたすら絵に打ち込む時間。明日か明後日には死に向かって発つときに凛として背筋を伸ばして、オレは絵を描くんだ、と。それはすごいですよ。それを実際に美術館に来て見て感じてもらいたいんです。たしかに、その“時間”は“氣”そのものですよ。今はインターネットだ、ケータイだとバタバタして落ち着かず、うわべだけのことに振り回されながらみんな死んでいく。そういう我々は、彼らの絵の前で立ちすくまざるを得ない。我々が失ったものの大きさ、それに気づくのですね。ところが、年間10万人も人が来てくれる美術館になってくると、ウワサだけで物事を判断する人たちが、インターネットかなんかで手軽に検索して取材に来る。実際に足を運んで彼らの絵を見て自分で何かを感じる… そういうことをしないままに、分かったつもりになってね。メディアに映像が流れたって、それは単なる情報です。情報は本物とは全く違うんです。もっと本物を見つめる時間を大事にしてもらいたい。世の中全体が空っぽの時代でね、これは自分を含めてですが、どうしようもないな、という気がします。
- 中川:
- 「無言館」で二十歳になった人たちの成人式をしておられるということですが、きっかけは今おっしゃったようなお気持ちからですか。
- 窪島:
 みどりの日に成人式を始めて、今年で5回目になります。「無言館」は、ある意味では青春美術館なのです。きっかけといいますか、僕は彼らの絵が戦争回顧の道具になったら可哀想だと思ったんです。こう言っては何ですが、肝心の絵を見ないで、絵にお尻を向けて、涙、涙の反戦平和演説をされてもねえ。確かに彼らは戦争の中で死んでいったのですから、理不尽なあの時代が二度と来ないようにと願うのは当然です。しかし、だからといって彼らは平和運動のため、戦争を語るだけのために絵を描いたのではないんですよ。ひたすら故郷の青い空、愛しい家族を描くことで、自己表現、つまり自分がここに生きている喜びを表現したのです。
みどりの日に成人式を始めて、今年で5回目になります。「無言館」は、ある意味では青春美術館なのです。きっかけといいますか、僕は彼らの絵が戦争回顧の道具になったら可哀想だと思ったんです。こう言っては何ですが、肝心の絵を見ないで、絵にお尻を向けて、涙、涙の反戦平和演説をされてもねえ。確かに彼らは戦争の中で死んでいったのですから、理不尽なあの時代が二度と来ないようにと願うのは当然です。しかし、だからといって彼らは平和運動のため、戦争を語るだけのために絵を描いたのではないんですよ。ひたすら故郷の青い空、愛しい家族を描くことで、自己表現、つまり自分がここに生きている喜びを表現したのです。- 中川:
- その画学生たちと同じ年頃の若い人たちが成人式に来て、そういう絵を見た感想は如何ですか。
- 窪島:
- 多くの人は押し黙ったまま帰りますよ。強烈なインパクトを受けるんでしょうね。中には「自分はまだまだ甘いと感じた」とか「一日一日を大事にしたい」とか言う。言葉は平凡ですが、雲の上の画学生はとても喜んでいるでしょうね。式には、ゲストに映画監督や作家の方をお呼びしてスピーチしていただくのですが、その方達も「自分自身が成人式を迎えたみたいな気がした」と、おっしゃるんです。若いから学ぶのではなく、人は死ぬまで自分を見つめるんですね。ゲストも若者も学ぶ、お互いに。そして、その主役は画学生なんです。ゲストの挨拶もいいですが、亡き画学生の無言の挨拶は大きいです。
<後略>
(2007年4月25日 「信濃デッサン館」にて 構成 須田玲子)











