2006年3月 「千葉 茂樹」さん

- 千葉 茂樹(ちば しげき)さん
1933年福島県生まれ。福島大学経済学部を経て、日本大学芸術学部映画学科卒業。新人シナリオ作家コンクールに入選後、新藤兼人に師事し1957年「一粒の麦」で脚本家デビュー。1974年「愛の養子たち」(文部省特選)で監督デビュー。1978年「マザー・テレサとその世界」で内外8つの映画賞を受賞。他に「アウシュビッツ・愛の奇蹟」、「豪日に架ける=愛の鉄道」、テレビアニメ番組「赤毛のアン」「ゼノ・限りなき愛を」など多数の作品を手がける。日本シナリオ作家協会会員。近代映画協会会員。SIGNS・JAPAN(日本カトリック・メディア協議会)会長。著書に「映画で地球を愛したい」など。
『映画を通して発信する「憎しみを愛に代えよう!」』
黒澤明監督「生きる」が決めた我が人生
- 中川:
- 千葉監督は、マザー・テレサのドキュメンタリーなど数々の映画を撮られていますが、どうして映画の道に進まれたのですか。
- 千葉:
- はじめは郷里の大学で経済を勉強していたんです。卒業したら市役所の職員になり安定した人生を歩むつもりでした。私は9人兄弟で、男は兄が一人です。実は、その兄が小児麻痺だったんですよ。
大学2年のある日、黒澤明の『生きる』を観て、強い衝撃を受けました。心奪われたまま、1時間ほど歩いて帰ってきて、ハッとしました。自転車を映画館前に置いてきたままだったのです。それほど興奮していました。そして、映画を勉強しようと決心したんです。父は30歳までやってダメなら戻ってきて兄の面倒を見てくれと言って、許してくれました。 - 中川:
- 一本の映画が人生を決めたのですね。
- 千葉:
- 千葉 まさに、そうです。それで日大芸術学部に編入し2年間学び卒業し、21歳で「新人シナリオコンクール」に応募したのです。
- 中川:
- シナリオですか。
- 千葉:
 福島弁は「そうだべえ」なんて言うでしょう。そういう方言を笑われましてね。シナリオを書いていれば、からかわれないからと(笑)。その応募作は思いがけず佳作に残りました。そして、審査員の新藤兼人監督が、「君はまだ甘い。でも、次の作品を期待しているよ」と言ってくれたのです。
福島弁は「そうだべえ」なんて言うでしょう。そういう方言を笑われましてね。シナリオを書いていれば、からかわれないからと(笑)。その応募作は思いがけず佳作に残りました。そして、審査員の新藤兼人監督が、「君はまだ甘い。でも、次の作品を期待しているよ」と言ってくれたのです。
この言葉に勇気を得て、セッセと書いては新藤監督に送りました。その度に監督は短いコメントを返してくれるのです。そして3年後、「今までの中で一番面白い」と電報をくださり、吉村公三郎監督に話を通してくれたのです。これが『一粒の麦』というタイトルで映画化されました。郷里でロケが行われ、私も方言指導を担当しました。24歳の時です。- 中川:
- 30歳までというお父様の条件をクリアできたわけで、それは良かったですね。どういう映画だったのですか。
- 千葉:
- 当時の集団就職を扱ったものです。金の卵として送り出された子供たちが、一旦都会に出ると辛い環境で働いているんですねえ。引率する郷里の先生は苦しい思いをしているのですよ。それをシナリオに書き、映画化されました。
その後は、「産休補助教員制度」の代用教員がテーマの『こころの山脈』です。代用教員は、お産で休んでいる先生の代わりで、子守役的な扱いを受けていました。そういうことでは、子供たちの教育はできないと思ったわけです。当時からずっとですが、私は人間の教育の問題に興味を持っています。人間をどう育てるか。映画を、教育にどう生かせるかです。
こうして15年ほどドラマのシナリオを書いているうちに、ベルギーで衝撃的なことに出合いました。人口900万のベルギーは全世帯数の4%がインド、韓国、中東、アフリカなどから養子受け入れとかかわっていました。実子が2人いる30代のある夫婦は、6人の国際養子たちを抱えて子育ての最中でした。 - 中川:
- ご自分のお子さんもいて、養子さんも育てている…。
- 千葉:
- そうです。「なぜ?」と訊ねると、「特別な理由はありません。もし、小さな子供がお腹を空かせて道端で泣いていたら、誰でも食べ物を用意するでしょう。それと同じです」と。さらに私が「もし、実子と養子が川でおぼれていたらどちらを先に助けますか」と訊ねると、「変な質問ですね。手の届く方から先に助けますよ」と。私は、もう恥ずかしくなりましたよ。
それで、そうだ、このドキュメンタリーを撮ろうと。ドキュメンタリーは作られたドラマにはない「現実の重み」がありますから。これが1974年に制作した『愛の養子たち』です。それから、マザー・テレサに繋がっていきました。養子の一人が、マザーの所から来ていたのです。でも、その頃の私は「マザー・テレサ、誰?」という感じでした。 - 中川:
- ノーベル平和賞をもらっておられますね。
- 千葉:
- ええ、でも受賞の前でしたから、日本で知っている人なんかほとんどいなかったんですよ。それで、ロンドンの書店で彼女の本と写真集を買ったら、すごく苛酷な所で働いているんですね。ホント?とびっくりしました。とにかくお会いしたいとインドに飛びました。
マザーは、小柄なのに、何というか、とても大きなオーラのようなものを発していて、迫力がありました。目がキラキラして、これはホンモノだと確信し、是非、ドキュメンタリーを撮りたいと思いました。それに、何となく、前にどこかで会ったような、懐かしい感じを覚えました。 - 中川:
- それは、よほどご縁のおありになる方だったのだと思いますよ。
- 千葉:
- この『マザー・テレサとその世界』を完成させるまでに、3年の歳月を費やしました。当時は「カトリックの尼さんが主人公?無理だね」と、どこもスポンサーになってくれませんでした。途方に暮れていたらバッタリと知り合いのシスター白井に会いまして、「それならウチが」と女子パウロ会が援助してくれることになりました。この出会いに始まって、実に多くの驚くような偶然に助けられました。インドでいつ下りるか分からない撮影許可を待っているときも、駐印新聞記者の奥さんが偶然、私の姉の同級生で、資金の乏しい私達をご自宅に泊めてくれました。
- 中川:
- 「偶然」というところに、見えない世界からの応援を感じますね。
- 千葉:
- まさにそうです。現役時代のマザー・テレサを記録した映画は、世界に3本しかありません。英国BBCと米国のNGO、そして我々のだけです。世界中から撮影許可願いのペーパーが山ほど来ていましたが。
毎回、門前払いの待ちぼうけという困難な中、私達はインドに滞在し2ヶ月間しがみついて交渉を重ねてきました。そして、ようやくインド政府の取材許可が取れて、大喜びで明日から撮影、という段取りになったら、思いがけない非常事態になりました。飛行機がニューデリーで降ろすべきだった荷物をそのままにして飛び立ってしまって、2週間経たないと戻らないというのですね。カメラもフィルムもなく、どうして撮影ができるの、と呆然としてしまいましたよ。
マザーは言いました、「では、一緒に祈りましょう」と。カメラマンは、「祈ると、カメラ出てくるのかよ…」と、すっかり意気消沈していましたよ。でも、他になすすべがないのですから、私達はマザーと並んで御聖堂で祈りました。祈って祈っているうちに、私はふと気づいたんです。マザー・テレサを撮りたいというのは分かるけれど、その対象となる路上で悲惨な生活を送っている貧困や病いに苦しんでいる人たちの痛み、辛さ、悲しみを私達は忘れていたんじゃないか。その方たちに許可も得ていなければ、お詫びもしていなかった。これはちょっと間違っていたなって思ったんです。
それまで「早く、早くカメラやフィルムを戻してください」とお祈りしていたのですが、止めました。「神様、もし本当にあなたが望まれているのなら、そして私達に資格があるのなら、撮影をお許しください。しかし、もしお望みでないのなら仕方ありません。私達は帰国します」と。 - 中川:
- 素晴らしい気づきですね。
- 千葉:
- そうしたらですよ、2日後に荷物がボンベイ(現在のムンバイ)で見つかって戻ってきたのです。
- 中川:
- えっ、そうですか!
- 千葉:
- その日は終生誓願式でした。若い女性たちが、修道女として終生、神に仕えますという誓いをする式です。そこでマザーは、こう言って彼女たちを励ましました。「あなた方は単なるソウシャルワーカーという職業に就いたのではありません。あなた方自身が選んだ生き方そのものなのです。喜びを持って実践しましょう」と。私は自分に言われたように、ハッとしました。自分の選んだ道は使命があって、その使命を喜んでちゃんと生きる、それが大事なのですね。
(後略)
(2006年1月12日 川崎市「日本映画学校」にて 構成 須田玲子)
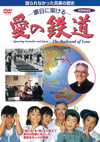
- DVDの紹介
豪日に架ける-愛の鉄道」 ¥5,000(税込) 発売元:映画「愛の鉄道」制作委員会 TEL.0742-45-7861











