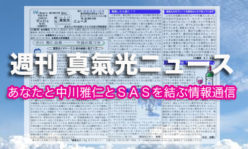「そうだやってみよう!」と、真氣光を受けていて閃きました。
私には課題があります。
それは乳癌手術をした際、リンパを数カ所切除しています。
その後遺症として左腕リンパ浮腫から発病する蜂窩織炎(ほうかしきえん)を度々発症しています。
発症したら症状を抑える為に入院をして点滴治療を繰り返していました。
お陰様で最近は高熱が出る症状はなくなり患部だけが腫れる症状となっていました。
しかし、何故発症がでるのか?氣を受けながら考えた時、心と身体のバランスが取れていない事にやっと気づきました。
そこで、身体の声を聞き、動と静のバランスを整える取り組みを始めました。
左腕にはシンキコーマッサージオイルアロマを使い、マッサージを続けていました。
そのマッサージをこのミニローラーヘッドでやってみたいと閃いたのです。
おまけにフェイスラインや首のリンパに沿ってマッサージも出来て小顔効果が現れる?!かもしれません。
これからの氣づきや効果が楽しみです。
(東京センター 佐久間郁)
[menu][次へ]
カテゴリー: その他いろいろ
いつも光の方へvol.2
私は、8月の氣配り画像に「いつも光の方へ」という言葉を入れました。
これは、たまたま妻がこの言葉を考えて、私の撮った写真からヒマワリの花畑を選んだのです。
その妻、中川みどりが去る9月24日朝7:00に亡くなりました。
ちょうど京都で開催する真氣光研修講座初日にあたる日でしたが、私は妻の旅立ちを見送り、講座開催にも間に合うことができました。
妻の「真氣光をしっかりお願いします」という思いを感じましたので、受講生の皆さんには、講座をすべて終えた最終日の挨拶で、お知らせした次第です。
妻は15年ほど前から、たびたび体調不良を訴えておりましたが、10年前に骨髄異形成症候群と診断されました。
この病気は血球を作れなくなる血液の癌で、妻の場合は血小板数が極端に低いという状態でしたが、輸血するなど特別な治療もすることなく定期的に受診する程度で、昨年夏まで何事もなく研修講座でのスタッフや「月刊ハイゲンキ」の制作などをしておりました。
しかし、病状が進み今年1月に骨髄移植、その後の経過は順調でしたが、8月中旬より感染症を併発し一時危篤状態に陥りました。
9月に入りその感染症を克服、会話ができるまで持ち直しておりましたが、臓器や血管のあちらこちらに負担が掛かっていたのでしょう。
最期は眠るように静かな旅立ちでした。
「いつも光の方へ」は、私への言葉になりました。
毎日の生活には、楽しいこともあれば辛いことも、光もあれば影もあります。
真氣光のエネルギーを十分に受け、それを利用して光の方向をしっかりと選択していこうと努力すること、妻は先代のもと次の役割を担っていることでしょうから、私もこれからますます精進しなければなりません。
生前、妻は研修講座やセミナーなどを通して、会員の皆様にはたいへんお世話になっておりましたから、一言お礼が言いたかったことと思います。
妻に代わりまして皆様に心からお礼申し上げます。
そして最後に、約30年、公私ともに支えてくれた妻に、心からの「ありがとう」の言葉を贈ります。
追記:「月刊ハイゲンキ」11月号の特別ページで詳しくお知らせするとともに、10/24(土)に「偲ぶ会」を東京センターで開催する予定です。
全国のセンターや会員の皆様にも映像を配信しますので、ぜひご参加ください。
(中川 雅仁)
[menu][次へ]
ひとくち歳時記「秋刀魚」
秋刀魚(さんま)は日本では秋の味覚を代表する大衆魚です。
秋刀魚という漢字表記は、「秋に獲れる刀のような形をした魚」との意味と考えられ、大正時代の詩人、佐藤春夫の「秋刀魚の歌」で広くこの漢字が知られるようになりました。
また落語の一つ「目黒のさんま」は、さんまという下魚(庶民は食べるが高貴な身分は食べない魚)を庶民的な流儀で無造作に調理したら美味かったが、殿様用に丁寧に調理したら不味かったという滑稽話。
殿様の「さんまは目黒に限る」という落ちです。
秋刀魚には、良質なタンパク質や脂質、そして血液をさらさらにするDHAが豊富で脳梗塞・心筋梗塞を予防し、脳細胞を活性化させ頭の回転を良くする効果もあるとされています。
最近のニュースで報道されているように、秋刀魚は中国や台湾などでも人気となり、外国漁船による公海での「先取り」により、日本の漁獲量は減少の一途をたどっています。
このままだと最早、大衆魚とは言われなくなるかもしれません。
(本社 加藤)
[menu][次へ]
ひとくち歳時記「重陽の節句」
9月9日は「重陽(ちょうよう)の節句」です。
古代中国では、陽数の極である九が重なる意味から重陽と言い、大変にめでたい日として旬の菊の花を飾ったり、菊酒を飲んで祝いました。
日本には天武天皇の頃に伝わり、平安時代には菊酒を飲み長寿を祈る「観菊会」が盛んに行われ、江戸時代に五節句のひとつになりました。
また「重陽の節句」は、秋祭りと一緒に祝うことが多かったので、人々はこの日を非常に尊び、「お」をつけて「おくんち」と呼んでいました。
かつて五節句の中で最も盛大であった「重陽の節句」も今や忘れ去られようとしています。
昔を偲んで菊を飾り、菊酒を飲んで、初秋を満喫するのも一興かと思います。
(本社 加藤)
[menu][次へ]
ひとくち歳時記「小暑」
二十四節気のひとつ、「小暑(しょうしょ)」は、七夕が行われる頃で今年は7月7日です。
梅雨明けが近く、この日から暑気に入り、暑さが厳しくなり始めます。
梅雨明け前の集中豪雨に見舞われることが多い一方、蓮の花が咲き、鷹の子の巣立ちが始まる頃でもあります。
またこの頃から「立秋」までが「暑中見舞い」を送る期間で、立秋を過ぎると「残暑お見舞い」となります。
梅雨が明けると、強い日差しとともに気温が一気に上がる時季のため、体調を崩しやすくなる頃でもあります。
暑さを乗り切るために、ネバネバ野菜(オクラや山芋)など滋養のあるものをしっかり食べて体力をつけておきたいものです。
(本社 加藤)
[menu][次へ]
おすすめ映画 『愛を積むひと』
只今公開中の映画です。
佐藤浩市と樋口可南子が夫婦役を演じ、北海道で第2の人生を送る熟年夫婦愛と絆を描いたヒューマンドラマ。
原作はエドワード・ムーニー・Jr.の小説「石を積むひと」。
ストーリーは東京の下町で営んでいた工場を閉
め、ゆったりとした老後生活を求めて北海道に移住してきた篤史と良子。
ガーデニングなどをして充実した毎日を楽しむ良子に対し、仕事一筋だった篤史は暇を持て余すばかり。
そんな夫を見かねた良子は、篤史に家の周りの石塀づくりを頼みます。
ところが、良子は持病である心臓病が悪化し、篤史の願いもむなしく亡くなってしまいます。
良子の死に絶望し、心を閉ざした篤史は、彼女が死の直前につづった自分宛の手紙を読んだことをきっかけに、周囲の人々や疎遠だった娘との関わりを取り戻していきます。
良子は亡くなった後、残された篤史のことを気遣って手紙に自分の思いをたくすことで、篤史は彼女の思いと共に前向きに生きていく…悲しみの中にもひとすじの希望の光をみいだして、石を一つずつ積むことで良子を思い出しながら、自分の心も癒していく…という映画です。
ぜひ観たいと思います。
ポスター
愛を積むひと 制作・配給 アスミック・エース/松竹
(東京センター 庄子)
[menu][次へ]