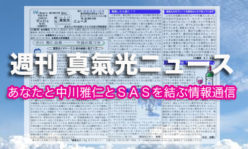きょうは朝から、早めに原稿を書き上げようと意気込んでいたのですが、友人からのクール便が届き、お礼のメールを書き上げていると郵便局の人が来て、そうこうしていると銀行から電話がかかってくるなど、いろいろな用事が舞い込んで、なかなかこの原稿が進まないのです。
忙しい時にはいろいろなことが舞い込んで来る「氣の法則」だと思っていたのですが、そのうちに何を書こうか考えが全くまとまらなくなってしまいました。
こういう時には、焦れば焦る程、わけがわからなくなるものです。
昔は、こういう状況に陥ると復帰するのに少々時間がかかっていましたが、ある時からは慣れたもので、焦っても仕方がないと開き直るようになりました。
そうすると、何処からかアイデアが降って湧いてくるのです。
きょうも、何を書こうか決まらないまま、お昼になってしまい、ふと時計を見て「あれ12時を過ぎている」と思った瞬間に、思いついた言葉が「腹が減っては戦ができぬ」でした。
十割蕎麦の乾麺があったことを思い出し、冷蔵庫の隅に残っていたトロロイモと、昨晩の残りのマイタケの天ぷらを入れて昼ご飯にすることにしました。
そして食べながら、これを題材にして書くことに決めたのです。
このことわざを辞典で調べてみると「しっかり腹ごしらえをしていなければ、良い仕事や働きはできないというたとえ。江戸末期の脚本に似た表現がある」と、あります。
昔から広く言われている言葉で、よく私の母も使っていたものです。
「戦」とありますが、肉体面、精神面で最もエネルギーを消耗する戦を仕事などの比喩として取り上げたのでしょう。
この言葉は、腹が減ると体はエネルギー不足になり、たくさんのエネルギーを消費する脳も良い働きができませんから、文字通りに「腹を減らすな」と解釈できます。
また、準備が大事だという捉え方もできます。
目先にたいへんなことがあると、そちらに氣をとられ肝心なところには意識を向けられません。
逆にマイナスの氣は、注意散漫にして肝心なことが出来ないように仕向けるものです。
ですからその手にのらないように、準備を怠らないようにしなければいけません。
さらには、準備という点では、真氣光を日頃からしっかり受けるということも大事です。
「氣の充電」とよく言っていますが、ある程度、光のようなエネルギーが浸透していかないと、マイナスの氣はプラスになって消えていきません。
精神的にも肉体的にもヤマを乗り越えるには、日頃の氣の充電はとても大事です。
あまり無頓着なのも困りますが、焦っても仕方がありませんので、しっかり準備して臨んでいただきたいと思います。