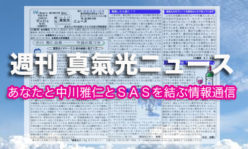先日開催した真氣光レッスンで、参加者Aさんの「いいこと探し」から「坊がつる賛歌」という歌の話がでました。 私は知らなかったので、当日は皆さんに「どんな歌?」と聞いたのでした。 あとで(ぼうがつる)を調べてみると『大分県竹田市にある標高約1,200mの高さに広がる盆地・湿原。 九重連山の主峰久住山と大船山等に囲まれており、阿蘇くじゅう国立公園に含まれている。 名称の「坊」とは寺院(久住山信仰の中核である法華院。 現在の法華院温泉)、「ツル」は「水流」で川のある平らな土地の意で、つまり法華院近辺の湿地帯といった意味の地名。 芹洋子がNHKの「みんなのうた」で歌った『坊がつる讃歌』で全国的に知られた』と、ありました。
坊がつる賛歌が生まれた背景には、山岳信仰と、それに伴う様々な人々の思いがあったのですね。 日本では昔から、山はただの自然の一部ではなく、神々が宿る場所として捉えられてきました。 そのため、山を訪れること自体が一種の修行や祈りとなり、人々の心を整えたり、エネルギーが高められると信じられていたのです。
歴史のある九州には古くから、いろいろな信仰の地があります。 そこに宿る神々とは、私がいつもお話しするプラスの氣という存在です。 九州ばかりではなく、どこの地にも存在し、たくさんの人を支え・応援しようとしてくれています。 しかし近年、このようなプラスの氣は、自然の崩壊、人々の意識や信仰心の変化などから、エネルギー不足に陥っていると、私は考えています。 また、そのような時代だからこそ【宇宙からの真氣光】というエネルギーが必要で、’86年に先代が夢でみて始め、私がこれを引き継いだのだと思うのです。
ところで、本紙面にAさん(いつも熊本センターで氣を受けていただいている)の「いいとこ探し」の文面を掲載します。 娘さんとご自身についての良い話の中に「最近この歌を口ずさんでいる自分に気づいた」とあります。 不思議ですが、ちょうど今年9月に大分県での研修講座、初開催が決定したばかりでした。 先代の言葉を借りれば、全ての事には意味があるということですから、見えないところでプラスの氣やマイナスの氣の働きがあって、そのご縁からAさんが口ずさむことになり、良いことも重なったことで、当日の「いいとこ探し」に投稿していただけたということでしょう。
大分での研修は9月14日(土)〜16日(月・祝)大分県杵築市「住吉浜リゾートパーク」での開催です。 興味がある方は、そちらへの参加も検討してみて下さい。 新たな発見・気づきと、さらなる氣の高まりを感じる貴重な体験が待っていることでしょう。