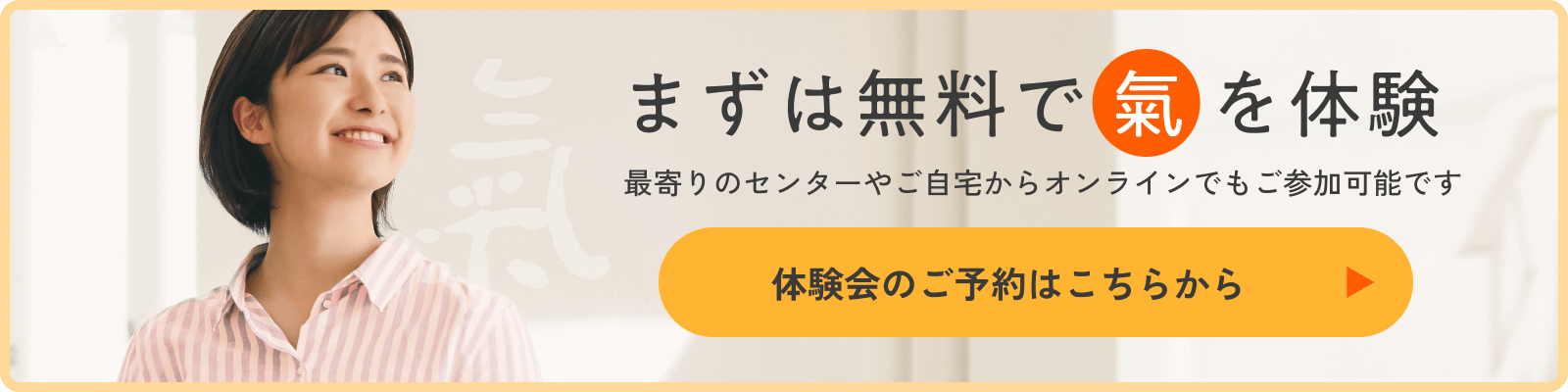「氣」の無料体験
最寄りのセンターやご自宅から
オンラインでもご参加可能です
 「氣」無料体験のご予約はこちら
「氣」無料体験のご予約はこちら
お問い合わせ
各種お問い合わせはこちらより承っております。
よくいただくご質問と、
その答えをよくあるご質問で紹介しています。
お問い合わせの前にご一読ください。
真氣光研修講座に関する
ご予約/お問い合わせ
その他のお問い合わせ
札幌センター :011-231-8150
東京センター :03-3980-8328
名古屋センター:052-203-8260
大阪センター :06-6944-1261
熊本センター :096-325-8455
セミナー関係 :03-3980-8328
受付時間 10:00〜18:00
(各センターの休業日を除く)