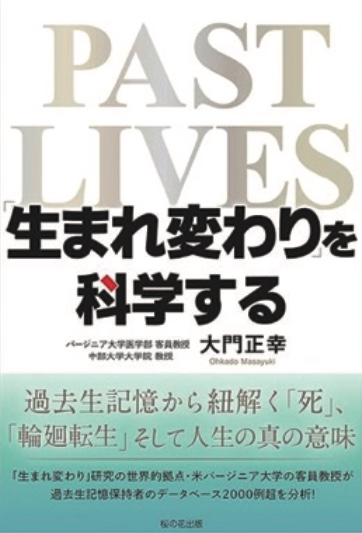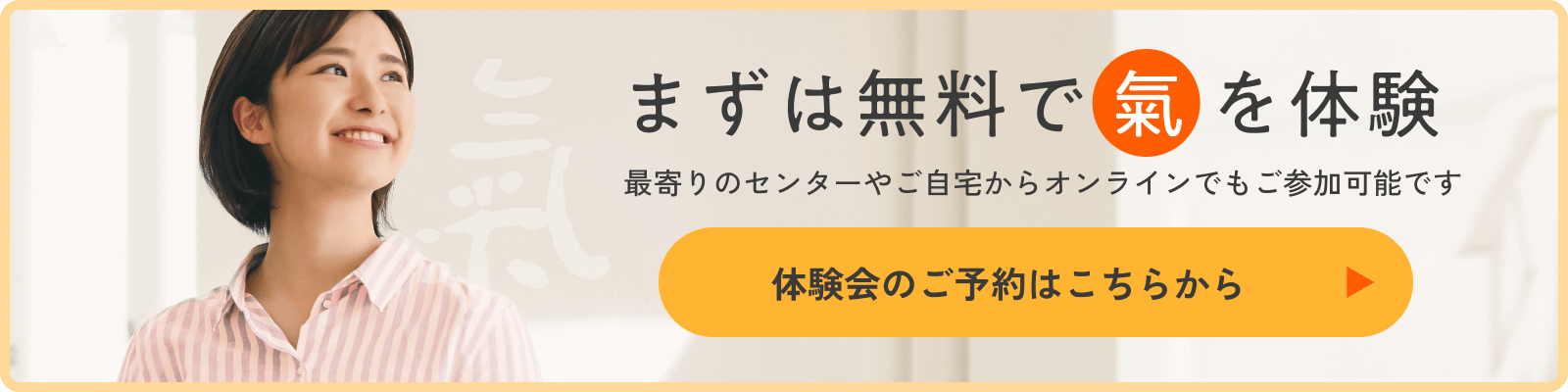3月「 大門 正幸」さん
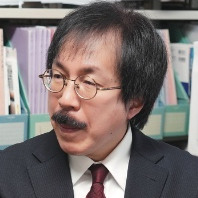
大門 正幸(おおかど・まさゆき)さん
中部大学大学院教授、米国バージニア大学医学部客員教授。1963年三重県伊勢市生まれ。もともとは唯物論だったが、長女の誕生、親友の死、次女が語る過去生記憶などの体験から肉体はなくなっても魂は存在し、自分たちを守ってくれていることを実感し、専門である言語研究に携わる一方で、生まれ変わりを科学的に検証し始める。著書『なぜ人は生まれ、そして死ぬのか』(宝島社)『生まれ変わりを科学する』(桜の花出版)など。
『人間の本質は意識や魂であると知ると人生が輝き出す』
過去生の記憶を語り出す子どもたちが増えている
- 中川:
- ご無沙汰しています。先生とは2015年2月号で対談させていただきました。ちょうど10年前です。 この間はテレビでも拝見しましたが、先生の研究されている「生まれ変わり」についての見方もずいぶんと変わってきたように思います。
- 大門:
-
私が過去生の記憶をもつお子さんに初めてインタビューしたのは2010年でした。トモ君という当時10歳の男の子です。日本に生れる前はイギリスで料理屋さんをやっている人の子どもだったという記憶をもっていました。イギリスでの両親のことや自分がイギリスで体験したいろいろな出来事を話すので、お母さまは心配して病院へ連れて行ったりしました。しかし、病院では過去生を扱ってませんから(笑)、お母さんの不安や心配は解消されませんでした。
- 中川:
-
 過去生のことは親御さんもわからないでしょうから戸惑いますよね。
過去生のことは親御さんもわからないでしょうから戸惑いますよね。 - 大門:
- 会長も見てくださった「クレイジージャーニー」というテレビ番組は怪しげなものとしてではなくまじめに過去生を扱ってくださいました。ユウ君という過去生の記憶をもつ10歳の男の子を取り上げた番組でした。あの番組を見たトモ君のお母さんは、自分にもユウ君の母親の心配する気持ちはよくわかるし、最後にユウ君と一緒に過去生の人物の家族に会えて本当に良かった、いいお仕事をされましたね、といった内容のうれしいメールをくださいました。
- 中川:
- ユウ君は3歳くらいから過去生のことを話すようになって、その内容から2011年9月11日の同時多発テロで亡くなった男性の生まれ変わりではないかと考えられ、先生と一緒にユウ君の過去生はだれだったのか探るという内容でしたね。最後には、ユウ君の過去生である可能性が非常に高いという方のご家族と面会するという感動的なお話でした。ユウ君と過去生の人物だと思われる方の間にはいろいろな共通点があって、びっくりしました。 面会のときにユウ君のそばにいたお母さんもほっとした表情でした。 たぶん、トモ君やユウ君のような子どもはほかにもたくさんいると思います。親は病気なんじゃないだろうかと不安になるでしょうが、ああいう番組があると、いきなり病院へ行くのではなく、先生に相談すると考えたりもするでしょうね。
- 大門:
- 今ではコンスタントにお話を聞くくらいはあちこちから連絡をいただきます。
- 中川:
- 生まれ変わりの研究はバージニア大学が世界的な拠点になっているわけですね。何人くらいの研究者がいるのですか。
- 大門:
-
現在は12人です。生まれ変わりだけでなくて臨死体験を中心にやっている人もいるし、霊媒現象を研究している人とか、脳の仕組みも含めて幅広くやっている人とか、いろんな方がいますね。 心とか意識というのは人間の体とは独立しているのではないか。それを追求するのが研究の目的のひとつです。そう考えざるを得ない事例がたくさんあるので、証拠固めをして、法則性を突き止め、独立しているなら心や意識とはどういうものか、そこまでいきたいと考えて研究が進んでいます。
- 中川:
- 心や意識は体から独立した存在ではないか。これは重要なポイントだと思います。
- 大門:
- そうですね。会長がやっておられる氣を考える上でもそこはポイントになるんでしょうね。氣は機械で測定できるようになりましたか。
- 中川:
- できないですね。どれくらい科学が進めばできるようになるでしょうか。今は、体験から知るしかありません。でも、体がすべてではなくて、心や意識は独立して存在し、生まれ変わりや氣の世界が本当にあるとわかれば、救われる人も多いと思うのですが。
- 大門:
- 多くの人の一番の恐怖は死ですからね。死に対する考え方が大切です。生き方も変わるはずです。今は南海トラフ地震がくると言われていて、みなさんいろいろ備えをしていると思いますが、100パーセント起こるとは限りません。その点、死は100パーセントですから、南海トラフ地震以上に備えをしておく必要があるのではないでしょうか。
- 中川:
- 日ごろから、死について、死後の世界や生まれ変わりの有無を含めて考えることが大事ですね。
- 大門:
- 死んでも次があると思うのと、死んだら終わりと思うのとでは、生活の仕方も違ってくるでしょうからね。
- 中川:
- 学生さんは先生の出ているテレビを見たり、本を読んだりして、どんな反応でしょうか。
- 大門:
- 授業で生まれ変わりを教えているわけではないので、限られた人数の学生とのやり取りから受ける印象でしかないのですが、ずいぶんと受け入れてくれているような気がしますね。データとしては、1950年と2000年のしっかりしたものがあります。2000名くらいインタビューしていて、年代もわけています。1950年の20代、死んでも意識が残ると考えている人が2割くらい。70代は4割くらいです。50年後、死んでも残ると考えているのが70代で3割くらい。20代は5割を超えています。男性と女性とを分けると、20代女性は8割くらいが死んでも終わりではないと答えています。
- 中川:
- このデータはどう解釈すればいいでしょうか。死後の世界だけではなく、生まれ変わりも信じる若い人が確実に増えているようですね。特に女性は顕著です。
- 大門:
-
昔は、死んでもおじいちゃんやおばあちゃんがそこらへんで見ているという感覚の人がたくさんいました。戦前は「七しょう報こく」という言葉もありました。七回生まれ変わって国に報じるということです。
生まれ変わりをどこまで信じていたかはともかく、気持ちとしては、今回命がなくなったとしても、もう一度生まれ変わってきて国に報じる、家族を守るという人が多かったんですね。精神性も高かった。戦後、GHQは、こんなことを考えている人が多いと日本を統治できない、と危機感をもち、死んだら終わりなんだと植え付けたのではないでしょうか。戦後80年になりますから、そんな洗脳も溶けてきて本来の日本人に戻ってきたように思います。若い人たちは何度も転生して魂の力を磨いてきたように感じますが、どうでしょうかね。 - 中川:
- 死んだら終わりだと思っていると、どうしても自分のことしか考えなくなりがちです。今、地球の環境や世界の平和を考える若者が増えてきているようにも思いますね。魂的に成長しているのかもしれません。ところで生まれ変わりの研究ですが、日本の事例がきっかけになっているということですが。
- 大門:
-
 生まれ変わりの問題について、世界で最初に系統立てて論じ、過去生の記憶を語る子どもに着目したのはバージニア大学の精神医学者、イアン・スティーブンソン博士でした。彼は論文の中で過去生の記憶を語る子どもの事例を7例紹介しました。その筆頭が今から200年も前、多摩郡中野村(現在の東京都八王子市東中野)に生まれた、当時8歳の勝五郎だったのです。(続きはハイゲンキマガジンで・・)
生まれ変わりの問題について、世界で最初に系統立てて論じ、過去生の記憶を語る子どもに着目したのはバージニア大学の精神医学者、イアン・スティーブンソン博士でした。彼は論文の中で過去生の記憶を語る子どもの事例を7例紹介しました。その筆頭が今から200年も前、多摩郡中野村(現在の東京都八王子市東中野)に生まれた、当時8歳の勝五郎だったのです。(続きはハイゲンキマガジンで・・)
愛知県春日井市の中部大学にて 構成/小原田泰久